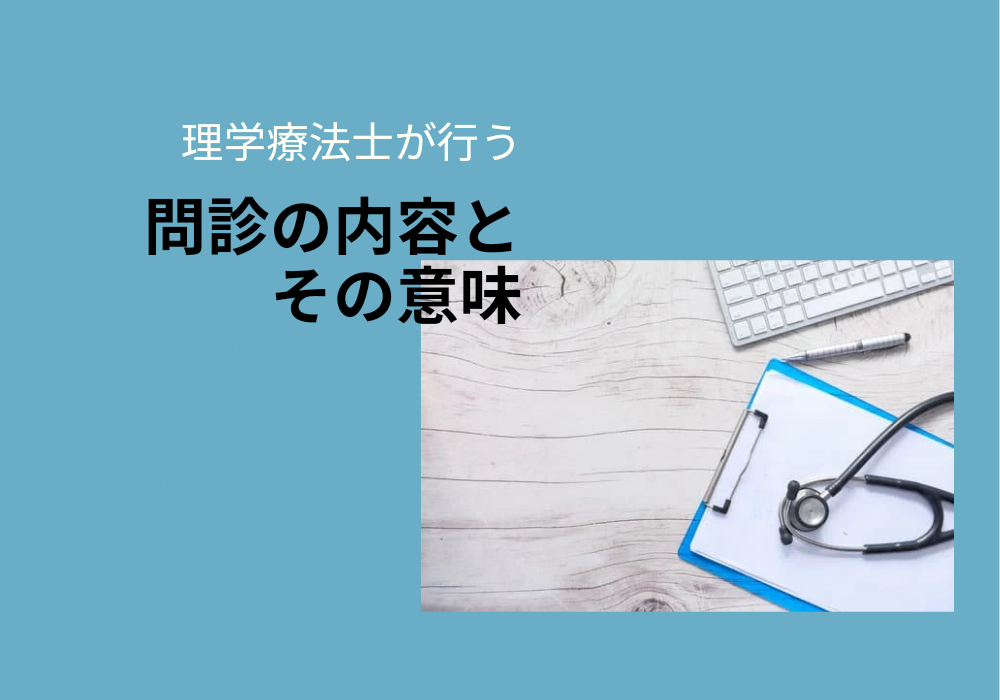タイトル通り、問診って何を聞けば良いのか問題。学生のときってまじでよくわからないですよね。筆者は、そもそもなぜ問診が必要なのかも、本当の意味でわかったのは、2年目の途中から。それまでは、先生や実習先の理学療法士、それまでの上司に聞いても、全然納得出来なかった。なんなら、検査もなぜやらなければならないかわからなかったです。そんな学生、新人PTは意外といるのかなと。そんな人達のために、まずは何で問診が必要なのかを具体的に書いていこうかなと。その後、具体的にどんなことを聞くのか、筆者である私が聞くことをすこーしだけ紹介しようと思います。
ちなみに、私の自己紹介をちょこっとだけしておくと…
- 7年目の理学療法士
- 認定理学療法士(運動器)取得
- ケースバイザーとして実習生の指導実施経験あり
- 関東ブロック理学療法学術大会で症例発表経験あり
- 整形外科は4か所で勤務経験あり(そろそろ5か所目が増えるかも…)
理学療法士としてはこんなもんかな。じゃ、早速言ってみましょう!
問診がなぜ必要か。
必要じゃないと思っていた過去
すこーしだけ、私が過去に思っていたことを紹介しようかと思います。
学校で、「問診は大事。しなさい。」って言われ、こんなことやあんなことを聞きなさいって言われてきたと思います。ですが、その問診って何に生かされてるの?って思ってました。そこが全くわからなかったんですよね。もう一度言う、“全く”ね。
新卒で理学療法士して、最初は色んな人の見学ついたりしたけど、問診をそもそもちゃんとしている人がいなかった。今行っている整形外科でもそう。みんな問診してねーじゃん!って思ってました。しかも、かるーくしてる人もいるけど。それを聞いたところで、アセスメントにも生かされてないし。それによって治療方針や治療内容を変えてる人なんていない。結局、問診したところで、やってること同じじゃね?って。今でも、周りはそんな人が多いです。だから学生も何を聞いていいかわからないんだと思います。しかも、それをカルテに書いている人もいないし。
現役のPTがそんなんじゃ、学生が何で問診が必要かなんてわかるわけねーじゃん!ってまだ思っています。はい、永遠の中二病です。(笑)
きっと、問診で何聞いていいかわからない人とかって、それがどこに生かされるのかとか、アセスメントや治療にどう反映させていいかわからないからだと思うんです。聞いたところで、その情報をどう扱ったらいいのかわからない。だから聞くことがなかったり、何を聞いていいかわからない。皆さん、違います?私はそうでした。
問診が必要だと感じたきっかけ
これが、クリニカルリーズニング(=臨床推論)というものに出会って、私の考えがまるっきり変わりました。ホント、180°、いや、540°くらい変わった。(結局一緒やねん。(笑))
それまでって画像評価やドクターの評価が重要だーみたいなことを言われ続けて来たけど、そこでは理学療法士には“機能評価が重要である”ということを学びました。あ、ざっくり言うとね?
もっと簡単に言うと、言えるかな?どう動かしたら痛くて、どう動かしたら痛くないのか。例えば、膝を曲げたら痛くて、伸ばしたら痛くない。とすると、それに関わってくる組織って違うよね、って感じ。
で、この機能評価で何で問診が重要か。それは、“推論”するから。問診の時点で、何が問題かを予測立てるんです。で、評価をしたらこうなるはずだ、というところまで予測を立てる。これがね、そんな単純じゃーないよ?結構みんな筋肉を問題にしたがるけど、痛みの質とかによって問題って変わってくるんです。びっくりだよね?私も最初はびっくりしたもん。だって学校で教えてもらってないから。(寝てただけかもしれんが…)
で、その問題によって、やることって全部変わるんだよね。しかも、検査も1つ1つから考えるのではなく、全部を合わせてどうなのか。例えば、ACLの検査だとしても、感度・特異度を考えてやって、合わせてどうか。もしACL損傷だったら、どうしたら負荷がかかるのか。じゃ、曲げたときに痛いの?伸ばしたときに痛いの?痛みは出ないはず?とか。まぁこれ以上詳しいことは以下で言いますね〜
実際、問診でどんなことを聞く?
ここでは具体例をあげること。そこから何を考えるのか。それらをあげていきます。他でもこんなことを聞きなさい〜っていうのはあると思いけど、そこから何をどう考えるかっていうのは少ないからね。ちょっとだけ挙げてみましょう。
あ、全部は無理よ?きりないから。(笑)
ここからは怪我ってことで進めていきます。何かしらの痛みなどに当てはめて考えてください。また、整形分野で考えていくので、中枢疾患などだとまた変わってくるかも…悪しからず…
受傷日
これはシンプルに、いつ怪我したか。そこから、病院を受診したのはいつか、リハビリが始まったのはいつか。
例えば、怪我してその日に受診したのか、少し経ってからしたのか。放っておけば治ると思ったけど改善しなかったのか、違う病院にかかっていたけど改善せずにこちらに来たのか、整骨院などに最初は通っていたのかなど…
その人の病院に対する考え方などもここから確認することが出来ます。
また、受傷日からどのくらい経っているかによって、今が炎症期なのか増殖期なのか、成熟期なのかもおおよそわかりますよね。それによってどの程度の治療をしていくかなども決まるし(治療の種類や強度、頻度、回数などなど)、痛みがどういうふうに出ているかも予想できます。炎症期の痛みだったとしたら、どんな感じで痛くなるか、明け方に痛みがあるかなど…そんなことも考えて聞けますよね。
これ以上は長くなってしまうので、やめておきましょう。
受傷機転
何で怪我をしたのか。例えば、「転んで手をついて」だとしても、普段からよく躓くのか、歩行が不安定なのか気になります。ですが、よそ見しててたまたま段差に躓いただけであれば、歩行に関しての問題は少ない可能性もあります。
一回の衝撃で怪我をしたのか、日々の繰り返しなのか。日々の繰り返しだとしたら、使い方も修正する必要があるかもしれません。ですが、一回の衝撃であれば、使い方に問題はそこまでないかもしれない。一回の衝撃も、例えばものすごい高さから着地してなのか、誰かにアタックされてなのかでも、考え方は変わってきます。
その部分を改善すればいのか、他の部分も確認しなければ再発しやすいのか、などを考えるためにもこれは必要です。
痛みの質、深さ、間欠的・持続的か
これボディーチャートに書く内容でもありますが…
例えば、原因組織によって痛みの質が変わります。鈍痛なのか、鋭利痛なのか、痛みが走る感じなのか、燃えるような痛みなのか…例えば、ビリビリするって言われたら、神経系の問題を疑いませんか?燃えるような痛みだとしたら、炎症かな?とか
深さによって、そこにある組織を考えられるので、これも質問します。
持続的か間欠的か、これも炎症期であれば持続的なはずであると考えられます。
これら3つは必ず聞くし、クリニカルリーズニングの中でもかなり重要ではないかなと思います。徒手系の理学療法の本には、これら3つによって考えられる原因組織がまとまっている教科書も合ったので、探してみるといいですね!
受傷時と比べて、現在はどうか
これは、怪我した最初と比べて、痛みや症状が治まってきているのか、強くなっているのか、良くなってきているのか。
例えばですが、時期的には炎症期が終わったはずなのに、痛みが強くなっているまたは変わらないとしたら?炎症を遅延させる何かが起こっているかもしれないです。それが、日常生活での何かなのか、その人行動からそうなっているのか…そうなると、どういった生活を送っているのか気になりませんか?はい、これでまた1個問診で聞きたいことが増えますよね。
主訴、展望
これらはなぜ聞くか、なんとなーくわかるかなと思います。
その人が何に一番困っているか。その問題がその日に解決できる問題なのか、時間がかかる問題なのか。主訴と会話の中で出てくる問題点が一致していない人もいます。例えば主訴では「痛いことが困る」と言っていても、会話の中では痛くて痛くて困っているという言葉は聞けない、「周りに迷惑をかけてしまうのが困っている」かもしれないです。これは、理学療法士側の主訴の聞き方によって出てくる答えは違ってくるので注意が必要かなと思います。「今一番困っていることは何ですか?」「この症状によって困っていることは何ですか?」「日常生活の中で困っていることは何ですか?」「最近大変なことは何ですか?」これらに対する答え、全部違ってきませんか?なので、主訴の聞き方には注意しましょう。
また展望(HOPE)は、主訴が痛くて困っているとしても、「歩けるようになりたい」「姿勢が良くなりたい」「長い時間歩けるようになりたい」とか、主訴が改善すれば到達できる目標ではない可能性もあります。実は展望は、その人が長年悩んでいたことや気になっていたことを言うことも多いです。なので、そこに関連があるのか、主訴を改善すれば展望も叶うのか。そこも考えることが必要です。
既往歴
これも意外と重要です。例えば、既往歴に糖尿病があったら、治癒過程が遅延しやすい可能性があります。他にも、呼吸器系・循環器系の問題があるとしたら、運動の負荷量はどの程度であれば可能か。
また、今回の症状は以前にも出たことがあるかも聞きます。もしあるとすれば、その時はどうしたのか。例えば、その時は放置したら良くなったから今回もなかなか来れなかったとすると、病気や疾患に対して、割と楽観的な気持ちでいるかもしれないです。例えば、以前行った病院で治りが良くなかったから来るのが遅くなったのであれば、病院や理学療法士、医療に対する期待が低い人かもしれません。そんな場合は1回で多少でも改善がなければ、2回目は来ない可能性が高かったりもします。逆に以前も通っていて、その時にいい経験(治りが良かった、理学療法士やドクターとの関係性が良かった)があれば、医療に対しての期待が高い可能性があります。それだけで、理学療法士に対する患者さんの態度・対応は変わってくるんですよね。
他にも、その他部位で他に怪我・病気・疾患はあったかも重要。今回の怪我は二次災害的なものの可能性も出てきます。例えば、1ヶ月前に股関節を痛めて、そこは気にならなくなったけど、今回は腰痛で来院。だとしたら、股関節の検査もしてみたくなるし、股関節を庇って腰痛に繋がったのかな…?と考えることも出来ます。もしかすると、それ以前に腰痛があったかもしれません。そうなると、腰痛→股関節痛→腰痛だとすれば、もともとは腰部に問題があって、それを庇うことで股関節痛に繋がってまた腰部になったのかも。
なので、既往歴は疾患名が付いていたものも大事ですが、付いていないもの、病院には行かなかったけどこんな症状もありました…というのも大事になります。そして、その順序・時系列も大事になるのでここも聞くようにしましょう。
その他問題・気になっていることがあるか
今回受診した問題以外で気になっていることはあるか。そこを改善したいか、どの程度気になっているか。
実は今回受診した以外の場所以外の方が気になっていたり、前から痛かったりする人って結構多いです。ドクターには伝えてないけど、伝えておきたいことはあるかなども聞いておくこと。「先生には言っていないけど、実は…」なんてこと、結構あるので。
それに、もしかすると、今回の怪我より気になっていることがあるかもしれません。そうなると、そちらを気にしたり見たりしてあげないと、患者さん・お客さんの満足度が低くなる可能性もあります。例えば、「今回の怪我の部分のリハビリが終わったら、気になってる方ができるように、また先生の診察で伝えてください」と言うだけで印象は変わりますよね。毎回のリハビリの際に「気になるって言っていたあっちはの症状、最近どうですか?」と聞いておくだけで印象は変わります。悪くなっているようならすぐに診察に促せるので、問題が大きくなる前に対処できる可能性もあります。それに、そちら側のリハビリをすることになった際、予測を立てておくことができるのですぐに治療に入れるかもしれません。
そんなことを含めてここも確認しておきましょう。
伝えておきたいこと・不安などはあるか
これは私は結構聞きます。例えば…「痛いのが苦手、優しくしてほしい」「リハビリは初めてで何をされるのかわからなくて怖い」「以前怖いドクター/理学療法士に当たった」「リハビリは高齢の人だけが受けるものだと思っていた」などなど、その人が医療やリハビリに付いてどんなイメージを持っていた・持っているのかがわかります。もし怖いのであれば、何が怖いのか。恐怖心があるとリラックスしにくいので、ROM検査や筋緊張検査に影響が出る可能性があります。また、痛みも強く・早い段階で出現する可能性も考えられます。
このあたりも聞いておくことで、相手を安心させられる可能性があります。そうすることで、信頼関係が早めにできやすくなるかもしれません。
最後に
今回書き出したことは、問診で聞くことの一部です。本当だったら、もっと沢山聞きます。それに、1つ1つに意味はなくても、合わせて考えると、意味が出てくる可能性もあります。
“大局観”ってやつですね。全てを考えて、合わせてどう考えるか。何が問題点と捉えるか。まずは何をしなければならないのか。そんなことを考える必要があるのではと思います。
そんな感じで、問診の内容とその意味について解説してみました!もし、他の問診や検査でも、なぜこれをするのかわからないから解説して!というものがあれば、メールかコメントか。残してくださ〜い!実習生や1年目の理学療法士で先輩やバイザーに聞かれたら、この通り答えても、問題ないはず!たぶんね!また、上記に記載した以外でも、考えられる理由などは沢山あります。なので自分でも考えてみてもらえると良いかなと!2つが合わさると、意味が変わってきたりもするので、注意ね!
ではでは、参考までに!